PFAS汚染と米軍基地、日米地位協定の「壁」を探る
前回の記事(靴・アウトドア・古着好き必見!日常に潜むPFASリスクと対策)でも紹介した「PFAS(有機フッ素化合物)」という単語。靴好きが愛用する防水スプレー、キャンプギアの撥水加工、古着の機能素材…。じつは僕らのスタイルの裏側にも潜んでいる現代の環境リスクだ。
そのPFAS、もっとやっかいなのが水道水や地下水からも高濃度で検出されている地域があるという話。実は東京でも、横浜でも、沖縄でも、そして、その汚染源としてしばしばニュースに登場するのが米軍基地。
なぜ米軍基地からPFASが?
実は、基地内で長年使用されてきた泡消火剤にPFASが含まれていた。航空機火災を想定した訓練などで使われ、地中へ染み込みやすい特性がある。世界ではすでに使用規制が進み、ドイツでは米軍基地でのPFAS汚染に対し、ドイツ政府が立ち入り調査し、米側に浄化費用を請求というケースも報じられている。
一方の日本はというと。
日米地位協定という“見えない壁”
日本では、日本の自治体や国が米軍基地内に立ち入って環境調査を行うことが極めて難しい。これは1960年に結ばれた日米地位協定が理由のひとつだ。ドイツやイタリアのような他の同盟国では、環境問題について自国側の権限がより強い。
しかし日本は…
- 基地内の立ち入りには米国側の許可が必要
- 汚染源の究明が進みにくい
- 費用負担が不明確になりがち
といった点が、専門家から不利な内容だと指摘され続けている。「え、日本ってこんなに弱い立場だったの?」と驚く読者もいるだろう。
横田空域の話を少しだけ
もうひとつ、日米関係を語る時によく出てくるのが横田空域。東京の上空の大部分を、管制権が米軍側に持たれているというものだ。「え、首都の空なのに自由に使えないの?」という不可解さが残るのは確か。PFASの問題を考える時、こうした敗戦直後の占領体制が今も続いている構図は、無関係ではないのかもしれない。

さらに、国際政治の世界ではジャパン・ハンドラーという言葉もある。米国の外交・安全保障関係者が、日本の政治家や官僚とコミュニケーションを取り、同盟の方向性を調整する役割のことだ。陰謀論めいて語られることもあるが、日本の政策がアメリカの意向に強く影響されているのでは?という疑問が常に付きまとうのも事実。そんな背景があるからこそ、PFAS問題で日本の対応が鈍いように感じられる…。という声が出てきても不思議ではない。
世界的なテーマだからこそ、知っておくべき
PFAS汚染はアメリカ、欧州、アジアの国々でも大問題になっている。国際基準ではよりシビアな規制が進む一方、日本ではまだ議論の途上。だからこそ今、ぼくらの健康、どこでつながっている? と問い直すタイミングなのかもしれない。スニーカーのケアを気にするように、キャンプギアを選ぶように、暮らしの延長線で世界の、そして日本の問題を覗いてみよう。







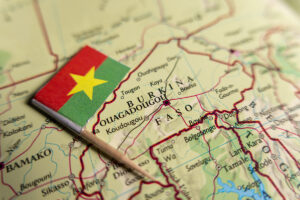





コメント